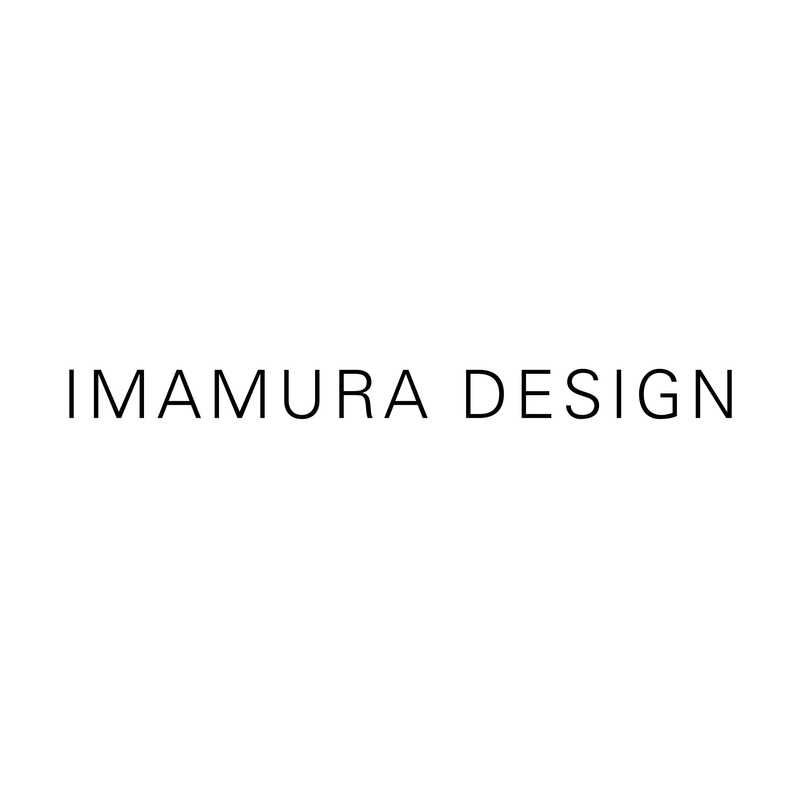再定義された町家 / 伝統を現代に迎える中京の町家 京町家の要素を継承しつつ新たな時代に求められる事柄にどのように対応していくか。この問いを静かに自問し、建てられたのが「再定義された町家」である。 京都市中京区の旧市街地型美観区域に位置した、東西に細長い敷地で、建築高は10m以下、勾配屋根と庇を取り入れるなどの建築規定が課されている。設計を担った建て主は、特定の土地や民族で生まれるORIGINALに興味を持ち、伝統的町家の「地味さ」に秘められたデザイン性の高さや無駄な要素を取り除いた実質的で合理的な美しさに強く惹かれてきた。そこで、京都の厳しい建築規定を自由にデザインできない障害ではなく再定義する機会とし、100年、200年の耐久性と構造性に加えて省エネルギー性能やデザイン性においても時代に影響されない持続性のある設計を試みた。 全体的な構造は、京町家などで多く見られる勾配屋根と庇を基本とする建築規定に基づいて設計し、耐久性のために鉄筋コンクリート構造(RC構造)を採用。屋根と庇は古くから京町家に使われている日本瓦一文字葺、外壁は外断熱材に濃目のグレー塗装で、外観を周りの環境に溶け込ませた。 内部の構成も伝統的町家と同じように、通りに面した西棟1階と2階が仕事場、東棟1階と2階に住居空間が配されている。西棟と東棟の間に苔庭(1階)とテラス(2階)を挟むことで、仕事場と住まいの距離を保った。また、炊事場の吹き抜けや玄関から裏に通じる通路(はしり)、苔庭と水庭から光と風を取り込む手法も伝統的町家に倣っている。既存の井戸水を苔庭散水と水庭の水盤に活用している。 一方で、現代における課題である環境的な持続可能性を追求すべく、省エネルギー住宅の要素を組み込んだ。ペアガラスサッシを用いた高性能な外断熱気密構造を採用し、コンクリートの蓄熱性の利用や熱交換換気システムを導入することで、消費電力を約70%削減できるようになっている。 内装においても、伝統とモダン、和と洋、繊細さと荒々しさ、豊かさと質素感(わびさび)という相反する要素を一つの空間に組み込む試みを行った。 コンクリート流し込み型枠に使用済みの合板を再利用することで表面に荒々しさが残った内壁に、数寄屋造りの障子を組み込み、温かみを出した。さらに、デザイナーである家主自身が手がけた照明器具とナガ族、ペルシャ遊牧民の古いテキスタイルコレクションで柔らかさを加えている。また、キッチンと化粧室のカウンターはひと昔に使われていた研ぎ出し技法を継承し、モダンな空間に旧式の感覚を取り込だ。 長い伝統に裏打ちされた持続可能性を保ちつつ、現代の課題を踏まえた「サステイナブルな町家」を多角的に再定義する試みは、年月を経ても続いていくだろう。(太田瑞穂) 継承した京町家の要素: - 勾配屋根と庇 - 日本瓦一文字葺 - 炊事場の吹き抜けと玄関から裏に通じる通路(はしり) - 光と風を取り込む1階の苔庭と水庭 - 既存の井戸水の活用 - 水庭の杉皮の塀 - 台所、流しの研ぎ出し仕上げ技法 - 旧式な台所とその収納 - 数寄屋造りの障子 - 引き戸仕様の窓、扉 省エネルギー住宅としての要素: - 高性能な外断熱 - 気密構造 - 熱交換換気システム - コンクリートの蓄熱性の利用 - 断熱ペアガラスサッシ