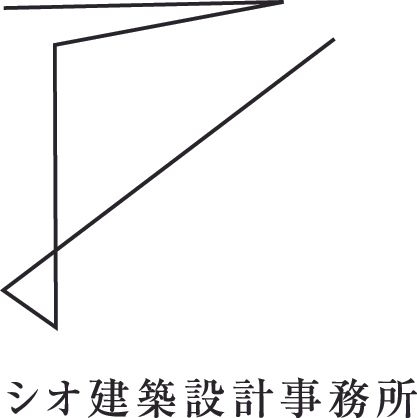
・小間の茶室で炭をくべる炭点前から、懐石料理、濃茶、薄茶という正式なお茶事、正式ではなくともお茶事を体験したいという人が体験のできる飲店食である。その他、お店で急にお稽古をしたくなった人、お茶に興味はあるが習っていない人、これから習いたい人など、誰でも気軽に茶道や日本文化を楽しむことができる。現在私たちの生活スタイルにおいて、和室や畳の部屋が少なくなり、正座をする機会がなくなった。このような現状にあわせて、このお店では正座をしなくても良い立礼席を基本としている。 ・客間は、広さの順から広間、三畳台目、三畳間の三室がある。広間は四畳半を基本としながら、その先には高さの異なる落掛で区切られた三つの立礼席がある、約十三畳程の部屋である。広間の奥に小間がつながっているように、落掛で一度仕切り、天井の仕上を変え、天井高を広間より下げる、また柱は皮付丸太を使うことで小間の雰囲気を出している。隅にある天袋が、この先に何かあるような気配と奥行感を出している。 各テーブルの間に畳を入れると全て座敷に、畳を入れる場所の組合せでテーブル席と座敷の併用もできる。その日の客の構成やお店のイベントに合わせて多様な使い方と同時に部屋が変化する。三畳台目には二種類の使い方がある。一方は、通常の畳の茶室として、もう一方は立礼席である。三畳台目の畳をあげると、下からベンチが現れ立礼席になる。炉畳をテーブルとして残し、それを囲む席である。点前座ももちろん立礼式である。客の好みやお店側の見せ方でどちらかを選ぶことができる。三畳間は、畳の間にある板の間を外して足を入れることで、立礼席になる茶室である。手前座隣の襖を開けると天井仕上げが繋がった一畳のバーが現れる。バーと併せて長四畳のカクテル席に変化するこの茶室では、バーテンダーは床の段差から生まれる畳のバーカウンターを使ってカクテルを振舞う。 もちろん、茶事の際は待合としても、三畳の小間としても使うことが出来る。 現代の住環境では全ての部屋でリビング、ダイニング、寝室というように用途が決まっている。しかし以前は、一つの八畳間で昼は居間、夕方は居間で食事をし、夜は布団を敷いて寝室になるように一つの部屋を様々な使い方をしてきた。茶事の場合も同様である。一つの茶室において時と場合で様々な使い方をする。限られた場所の中で様々な展開を楽しむことができるこのスタイルは、日本文化の再発見が行われている昨今、日本建築を再考する機会を与えるとともに都市部における建築の使い方の提案である。