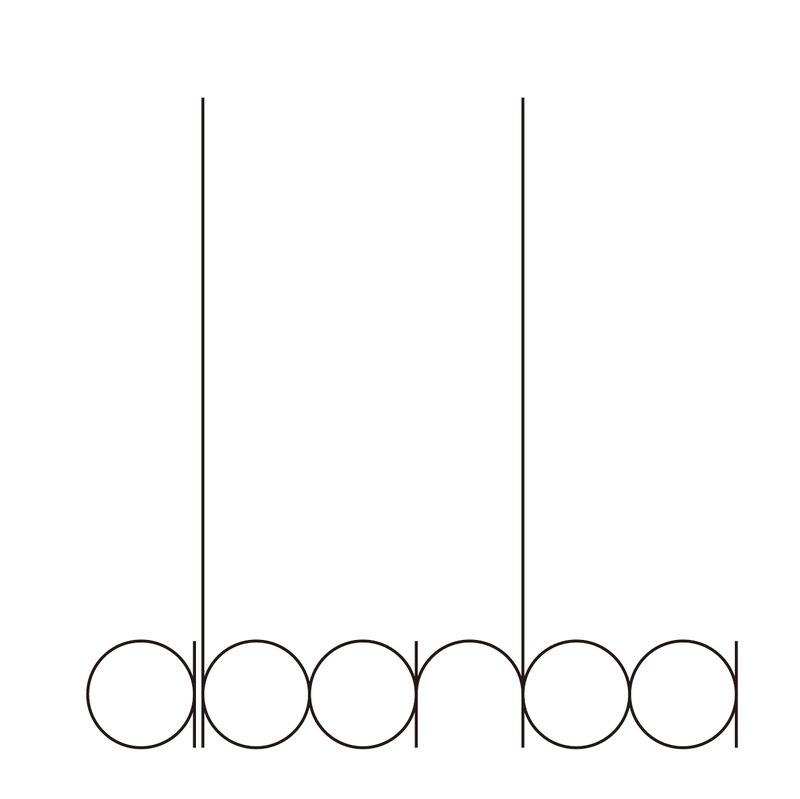■博物館の機能を補完する多目的ホール かつて横浜の街を走っていた路面電車の展示保存施設である横浜市電保存館は、実際の車両や、大規模な鉄道ジオラマなど、充実した展示がある一方で、ワークショップや、レクチャーなどのイベントをおこなうスペースの不足や、静かに鑑賞する人と、体験型展示を楽しむ子どもの棲み分けなどの問題があり、その解決のために、しでんほーるが計画された。 ■住宅スケールのボリュームの集合としてのホール 敷地は既存の市電保存館の駐車場であり、できるだけ駐車台数を減らすことなく新築することと、周辺は住宅街のため、スケールを逸脱することなく、周辺と馴染みながら、道路から少し奥まった位置にある既存の保存館の存在をアピールすることのできる建物が求められた。そこで、建物を大きさの異なる4つのボリュームに分割し、互いに支えあうことで、1階の駐車場と、2階の多目的ホールといった大きなスペースを作り出す構成にしている。各ボリュームは、垂直の2つの壁面が円形に切りかかれた形状をしており、1階で建物が接地する部分を減らし、駐車場を確保しながら、2階に大きく広がりのあるスペースを作り出す。開口部は、1階と2階を連続的に見せるとともに、ホールでおこなわれている活動が、周囲から見えることで、建物の外観と共に、行きかう人々に市電保存館の存在を示すようになっている。 ■交わる緩やかな境界 ホールは、建物を構成する4つのボリュームが、交差することで生まれる天井が特徴的な空間となっている。広さは、社会科見学の際などに、小学校3クラスが同時に食事をしたり、授業することができるサイズで決まっている。そうした大勢での一体利用の他に、小規模なワークショップや、日常的に複数の家族が同時に使う際などに、梁や各ボリュームの天井高さの違いと、貼り分けられたフローリングのパターンが、緩やかに空間を仕切るきっかけとなるように計画している。 ■ズレからの排煙、採光、通風 交差するボリュームの隙間には、排煙を兼ねたハイサイドライトを設けており、暗くなりがちなホールの中央にも自然光が落ちることで、照明の点灯時間を抑え、建物外周のボリュームの交差する部分に設けた開口部と、ハイサイドライトを開放することで、自然に風が流れるようにしている。