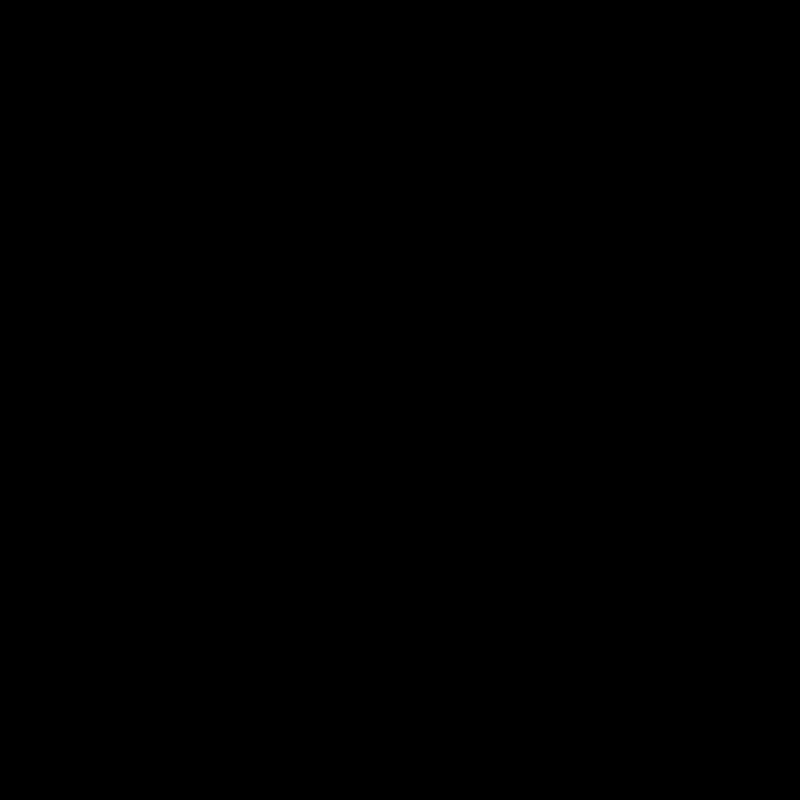[生きるための環境]をつくる開口 壁に開口を開けることは、生きるための環境をつくる行為だと思う。 内部に風や光、風景が入り込み、暮らしていて気持ちが良いという根源的な住宅。 この住宅では、隣地の建物と視線が交差しないように調整した開口と、周辺も関係なしに、この位置にあると光や風が気持ちが良いだろうと感覚的設けた開口もある。 その矛盾した両者を同居させることで隣家との間合い、都市との距離感、親と子の距離を離しつつ繋ぐ関係を目指した。 [小さな敷地]としての余白 雑居ビル、マンション、ホテルが建ち並ぶ都心の大通り沿いに計画した2世帯住宅である。 外周にテラスや縦動線などを配置した、入れ子のような平面構成になっている。 バッファーとしてのテラス、それと連続する屋外階段、大きくゆとりのある内部階段と踊り場をもち、その隙間に各世帯の占有空間、2世帯の共有空間を挿入した。 各階のテラスを介して、世帯同士のゆるいつながりを生み出している。 テラスは半外部でありながら、内部的な仕上げで統一し、内部階段と踊り場は、隣地の建物に囲まれた裏手にはあるものの、開口を多数設けることで、外部的な明るい空間とした。 また、親世帯の住居である2階と、子世帯の住居である4・5階の間には、あえて用途を規定しない余白の階層を挿入している。 用途のない場所は、この住宅の床面積の半分近くを占め、そこを「小さな敷地」と呼ぶことにした。 家の中に小さな敷地をいくつも設けることで、我々が建築を考えるのと同じように、使い手はその場所を自ら設計して生活をしていく。 幅広でゆとりのある階段でお茶を飲みながら本を読んだり、部屋の様な大きな踊り場で仕事をしたり、内部の様なテラスでランチをしたり、余白の3階を写真スタジオとして利用したり。 建物の中に「開口を開け」「小さな敷地」を持つことで本能的な生活の風景を生み出し、機能を超えた「生きるための環境」をつくることを目指した。