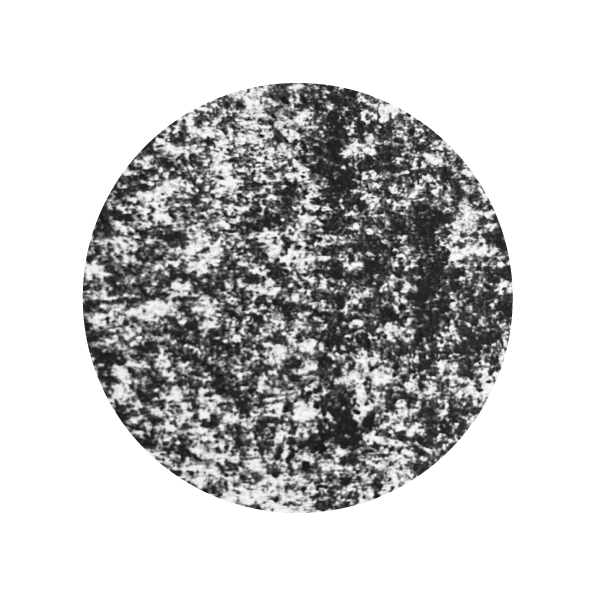PROJECT MEMBER
この建物は、自分の時間と向き合う宿「こもる五所川原」として民家から改修された。 静寂を謳歌し、自然と共に流れる時間を慈しみ、一晩を過ごす。特別なものは何もないかもしれないが、急がず、ゆっくりと心を通わせることができる場所。日常から、仕事から、ルーティーンからそっと離れてみると自分の鼓動が聞こえ始める。そんな瞬間と向き合える空間を目指した。本州最北端の地で提供するホスピタリティーはささやかだけど母のように心あたたかく、人間の営みと風土を大切にする。「こもる五所川原」は全5部屋の小さな宿である。 既存建物は林檎畑や水田が広がる津軽平野の中、五所川原市の中心街から南に車で15分ほどの集落の一角にある築50年ほどの木造2階建て民家。建築主の祖父母がかつて暮らしていたが5年ほど空き家の状態となっていた。建築主の祖父は林檎農家でもあったことから既存建物の西側には林檎倉庫が隣接していた。住居として利用されていた空間には数えきれない暮らしの痕跡が残っており、それらの記憶を引き継ぎながら、新しく宿泊施設としてどう魅力を伝えていけるかを意識した。 既存建物は周辺の建物と比較しても日本の地方都市における戦後の”典型的な民家”である。ここでは典型的という概念についての詳細説明は避けるが、このありふれた、もしかすると昨今もっとも空き家となりがちとなっている世代の民家と言える既存建物をどう操作し、編集するかが設計の重要なテーマであった。 建物の外観とそれから想定しうる建物内部の構成の不一致を狙う、”ズレ”を起こすことでより記憶に残る空間体験を作れるのではないかと思案した。南側立面を見ると1階居室部分の窓は新設した塀によって隠れている為見ることができず開口部の存在は想定できないが、居室内部に入ると初めて窓の大きさを知ることになる。また、既存の木造2階建てのフォルムを改修後も維持していることから、外観からすると1階と2階に上下綺麗に別れて居室があるように見えるが、内部に入ると2階の窓は実は1階にある居室の頂側窓であったりとする。 既存の建物の内部は全て床が貼られていたが、改修において建物西側の玄関、ダイニング、浴室、キッチンは全て床を無くしコンクリート土間で墨入りモルタル仕上げとした。床を下げることで玄関・ダイニング部分など公共性の高い空間の天井高を確保し開放感を演出した。玄関からひと繋がりとなっているキッチンは2mの暖簾3本によって緩やかに仕切られている。