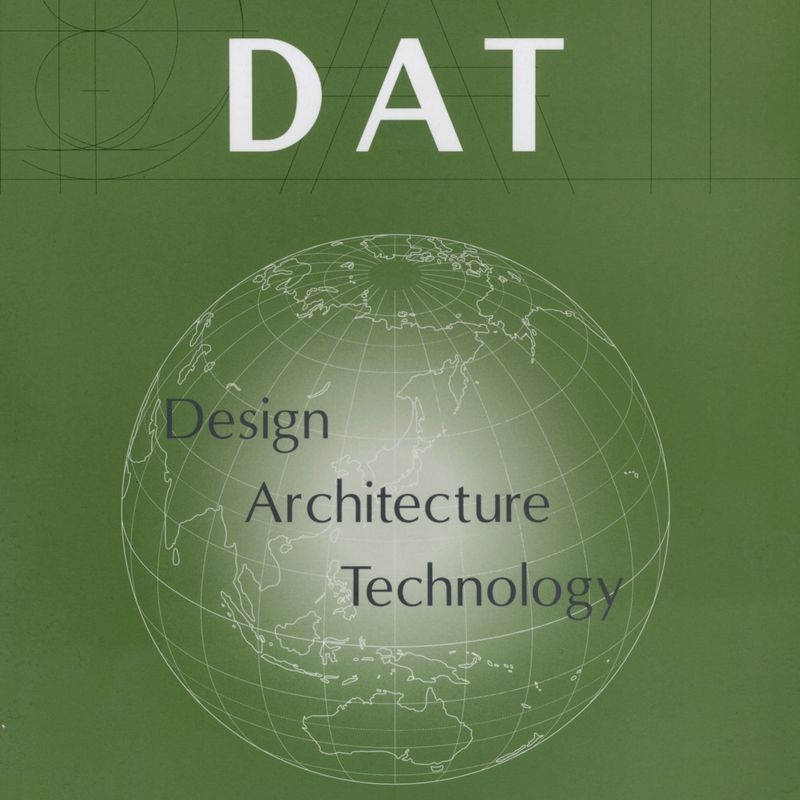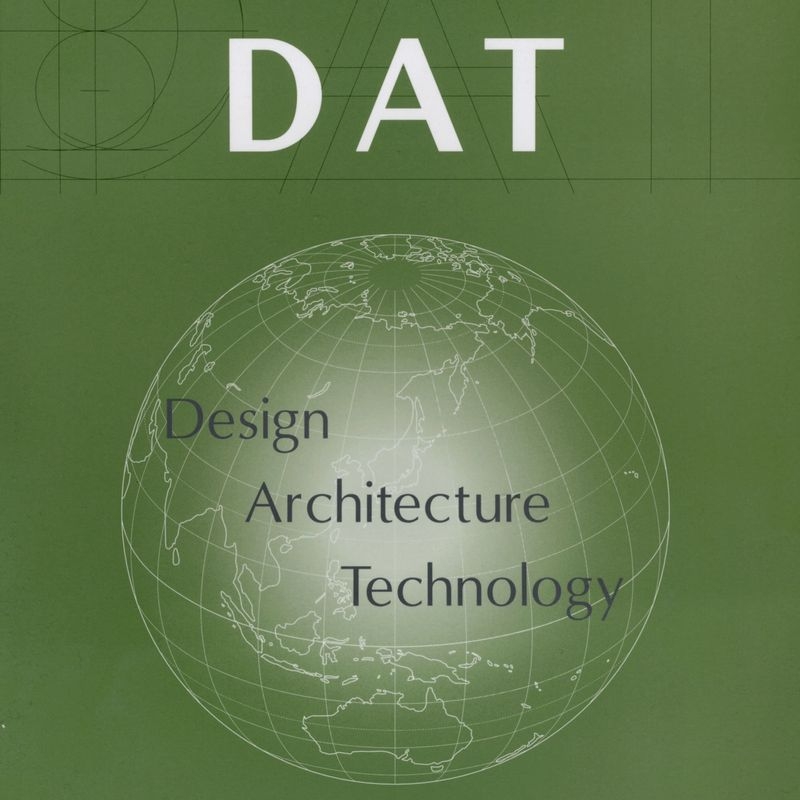
PROJECT MEMBER
■敷地条件 この住宅は、長野県上田市の市街から千曲川を渡った辺、新幹線の乗り入れ以降、宅地化が進む場所に建つ。敷地は、①南北で二方向で接道する。このうち北側は、近隣宅地共有の車用に設けられた位置指定道路で、歩行により地域の基幹道路(国道)とアクセスするには南側水路沿いの生活道路が近い。②敷地周辺では、古い住宅、田圃、自動車工場、宅地で、今後の宅地化や建替が想定される。また、③この地は寒冷地に属し、毎冬約40㎝程度積雪する。雪質は軽く風に乗って吹付けることが多い。 ■配置・平面計画 配置・平面計画では、敷地性状や自然環境の特性と調停しながら全体像を考えた。 結果、①については、南北それぞれの道の性格に対応して、北側に公的な玄関、南側に私的意味合いの強い出入口を設定することにした。また、②、③については、敷地外部に全くオープンな状態の庭や開口を避けて建築内部に中庭を設け、これを回遊する形式とした。 ここでの中庭は、コンサバトリーより南側生活通路に開き、日常的なアクティビティの高い路地のような役割を意図している。同時に中庭は、建築内部に大きく開き、雪の吹付けを考慮して最小限に止めた外壁の開口を通風・採光面で補い、開口部に用いたスライドサッシを大きく引き分けることで、東西に面するリビング・子供室の自由な往来と空間的な連続性を確保すると同時に、閉時は視線を拡散する役割も果たしている。 建具により空間相互の関係を連続・拡散することは、子供が幼く親密な保護を要するクライアント家族の現在と、プライバシーが求められる将来、双方の居住意識に対応するためでもある。加えて、間仕切りの上部をガラス欄間とし、断面的な連続性を持たせたり、白く塗装し、拡散的な印象を強めるといった操作もこうした意図を反映している。 ■断面計画 断面計画では、南北方向に架かるアーチ形状を設定した。 この形状は、隣地に近い東西方向への落雪を防ぎ、間仕切り壁を挿入するだけで用途ごとに必要高さの異なる内部空間を効率よく区分できる。 構造は、C型綱(150㎜×65㎜)の抱合わせ材をアーチ型の梁に沿って455㎜ピッチで配し、これを合板で挟んだハニカム形式の曲面を、建築外形に配した100㎜角の柱で支えている。また、間仕切り壁は木軸とし、家族の将来的な変容にも対応できるようにしている。 ■シェルターとして 周辺では区画整理された土地に商品化住宅が建ちはじめている。新幹線で1.5時間。距離感の喪失とともに景観が均質化されて行く。希薄になりがちな場所性と調停した形式を見出すならば、この場所における住宅建設の原初的な意義に立ち返った考察が必要であるように感じられた。 この住宅の出発点はシェルターである。住宅に求められる概念の内、自然環境の厳しい地域ではこうした概念が重視されるのではないかと考えた。といっても頑強な外郭によって周囲と隔絶した内部環境をつくることを目的とするものではない。 敷地性状や自然環境、ライフスタイルと細かく調停しながら、かといって調停結果が、形態や仕上げに混在した印象を与えない単純な形式を目指した。