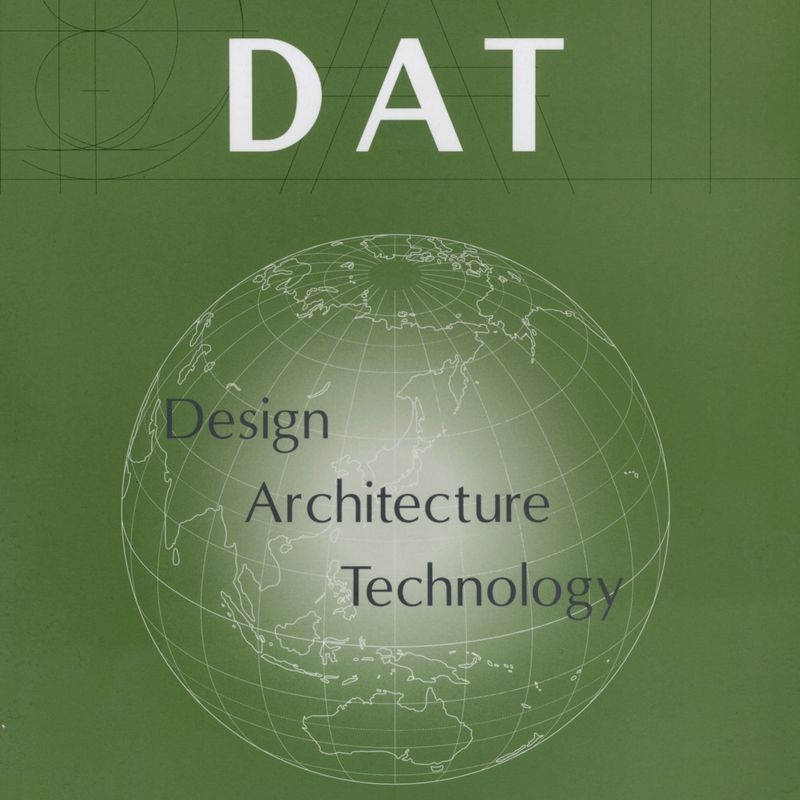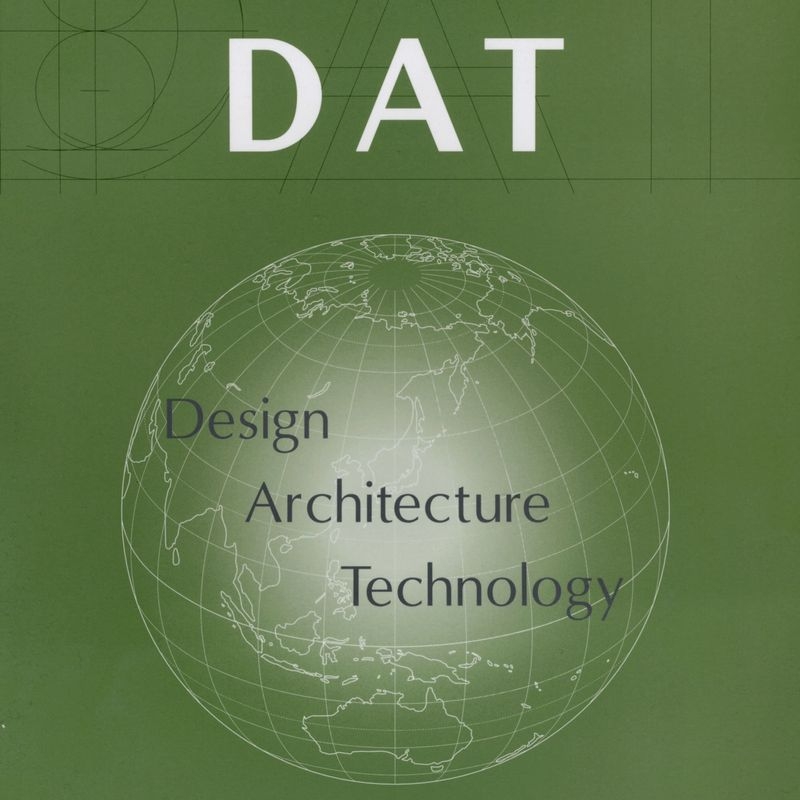
PROJECT MEMBER
都心の住宅地にある敷地周辺は、寺院が多く、蔵を残した住宅が観られたりと、歴史的な土壌を感じさせる反面、幅員4mに満たない路地が入り組んだ住宅密集地も残っており、こうした地区を抜け、幅員約7.5mの前面道路に出ると急に開けた感じがする。 前面道路は昼間でも車が少なく、沿道の住宅に自然光と静かな環境を与えている。 クライアントは、この場所に2世帯住宅を計画された。 計画当初の主な要望は、①奥行きの深い長方形の敷地の中で十分な自然光を確保すること、②6000冊の蔵書を収めることの2点であったが、限られた規模に集中する人と物の距離感をどう確保するかについても気になった。 ここでは、まず敷地境界線の西と北にかかる斜線をかわし、車2台分の駐車場に必要な間口をとって建ちあげた最大の直方体ボリュームを、3層の鉄骨ラーメン構造で造り、居住と家財道具のスペースをゾーニングすることからはじめた。 ゾーニングではまず、建築の南東角に採光・通風のコアとなる光庭を設定した。 また、平面を極力コンパクト化し、空いた隙間を利用して2、3階をつなぐ小さな2つの吹抜けも設定した。加えて、2つの階段と2、3階のガラス床を加えた小さな連なりが、長い建築の深部に自然光を導き、通風や家族の気配を循環させる役割を果たしている。 6000冊の蔵書に対しては、コレクションするというより、自由に手に取れる気軽な読書環境が求められた。 ここでは、リラックスした姿勢で雑誌を読んだり、時に腰を据えて専門書を読んだりと、場所を選択できる住宅の特性を活かし、空間用途と一致した蔵書内容の本棚を各所に点在させている。また、空間は引き戸や床のレベル差などで曖昧に区切り、住み手が本を片手に移動しながら、気に入った場所や新しい空間利用の在り方を発見できるようにも考えた。 都心の限られたスペースに人と物が集中する2世帯住宅では、その内部に大胆な連なりを造ることは難しい。しかしながら、他者を視覚的に確認できない小さな連なりであっても、気配や物理的な距離以上の開放感を共有することはできる。この2世帯住宅では、こうした効果を用いて、世帯間、家族間に適度な距離を創り出している。