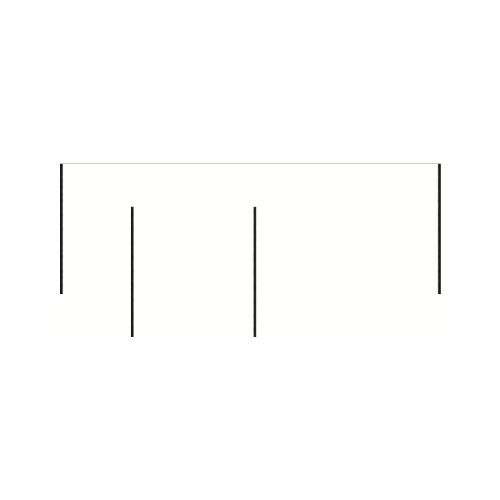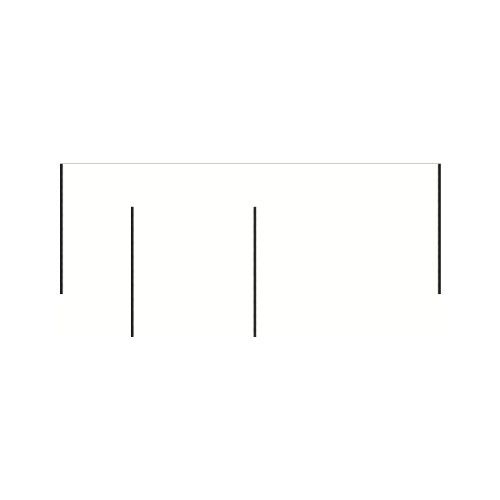
沖縄本島中部の読谷村に建つ、家族4人のための木造平屋の住宅である。 RC造で住宅を建てることが主流の沖縄で、建築主は木造で住宅を建てることを望んでいた。 それは木造の方がコストが安いからといった、どちらかというとネガティブな理由からではなく(むしろ沖縄ではRCよりも木造の方が建設コストが高いか、あるいは大差がない)、「私たち夫婦と一緒に歳をとり、循環する家にしたい」「いずれ子は巣立ち二人の生活になる。その時に暮らしやすい家にしたい」という、建築主の人生観から導かれたポジティブでサスティナブルな思考からの希望であった。 敷地は琉球王朝時代の宿場「喜名番所」が在った読谷村喜名という地域の中心部の住宅街に位置し、北が幅員5mの道路、東と南はRC造2階建ての住宅、西には駐車場をはさんでRC造3階建のアパートと、3方を堅牢なコンクリートの塊に取り囲まれていた。 沖縄でRC造が主流となったのは、台風対策からである。 戦前は沖縄でも木造が主流で、猛風に耐えるために敷地地盤面を周囲より低くして風の影響を軽減し、さらに敷地の周囲に「フクギ」を植え防風林を形成していた。 偶然ではあるが本敷地も地盤が道路よりも低く、周囲をまるでフクギのようなRCの住宅に囲まれていたことから、台風への備えが既に出来上がっているかのような周辺環境であった。 しかしながら、近年の台風は強大化しつつあり、予断を許さない。 このような状況から、風の影響を軽減するために高さをできるだけ低くおさえ、耐風圧性を高めるために外周部を耐力壁で固めた箱型の形状が導かれた。 外壁は杉板の押縁張りが採用され、「木造」という構造をストレートに表現した外観となり、RC住宅に囲まれた町並みにあって異彩を放っている。 採光と通風を確保するために箱型形状の中心に中庭を設け、中庭に面する部分はすべて開口部とした。 中庭を挟んで南側が個室棟、中心に和室、北側に天井高を高くしたリビング棟を配置している。 内部空間はおおきな体積のワンルームが理想的だと考えていた。 沖縄の真上から突き刺さるような光や、海を感じる心地よい風、湿り気を含んだ空気がおおらかに室内を循環し通り抜けていくような空間のあり方が、沖縄の気候に適しているのではないかと考えていたからである。 そこで中庭もひとつの空間として捉え、個室空間も壁で仕切るのではなく建具で間仕切り、中庭を介してすべての空間がおおらかに繋がるような構成としたことで、光や風や湿気、そして家族の気配が住宅全体を通り抜けながらも充満しているような、ゆるやかな空気感に満ちた住宅ができたと考えている。 近年、内地(本州や九州・四国など)から住宅メーカーの参入が増加し、沖縄でも徐々に木造住宅の比率が増えている。 内地に比べ木造住宅を建てるには過酷な自然環境の沖縄で、現代の工法や技術を用いた沖縄らしい木造住宅の在り方のひとつを提示できたのではないかと思っている。