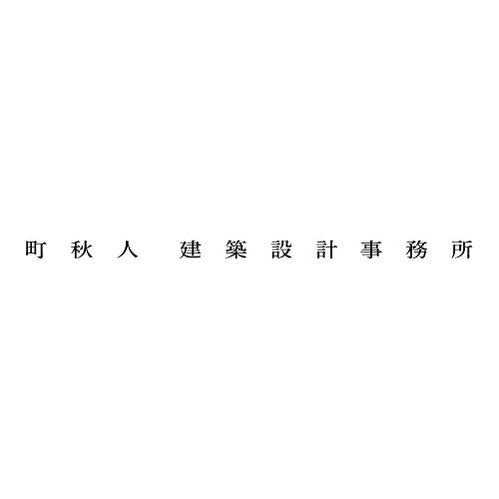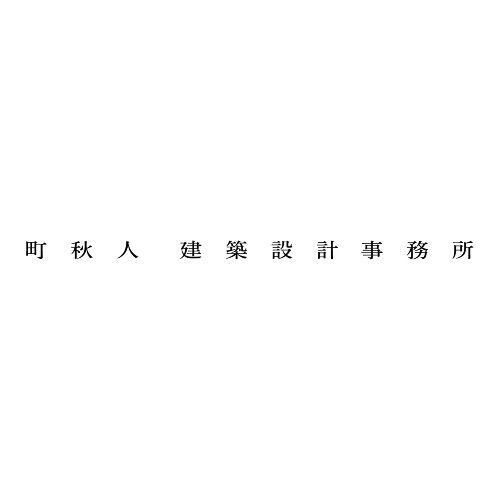
近所の方が畳の交換相談に来て店主と話をしている。 畳屋さんは製造工場というよりは商店に近いのかもしれない。 どの地域にも畳屋さんが一軒はあり、幼い頃には開放的なガラスサッシ越しに中の様子を興味深く覗いた記憶もある。 考えてみると畳という存在は建築を構成する要素の中では メンテナンスフリー(永遠)を理想とせず交換や張り替えを前提としている点で住み手が継続的に状態を見ながら関与できる、今となっては稀な存在なのかもしれない。 施主である松葉畳店さんは 一般的な畳の他、イ草をつかった畳雑貨などの製造販売と日々精力的に活動している畳屋さんである。 今回は元々先代が建てた平屋建ての畳作業場が老朽化したことと、畳やイ草の魅力をさらに伝えていく場が必要となり 建替える計画となった、畳作業場の他、奥さんが手掛けている畳雑貨の作業場、 雑貨を販売する店舗とそれぞれのスペースを一つの建物の中に求められた。 敷地は静岡県焼津市、県道に面し、開口が狭く奥行きのある町屋形式の敷地である。 元々建物は道路からセットバックしていたが 今回の計画ではより街へと地続きとなるように道路側に寄せた配置とした。 敷地面積は限られていた為、必然的にそれぞれの用途を上に積み上げていくことになり、それぞれの用途をずらしながら積層した。 畳の素材や製造過程を見ながら上へと登っていき、全体を体感しながらも それぞれの場が独立してダイレクトに街へと繋がっていく状態を試みた。 構造は住宅スケールの鉄骨造二階建てである、柱や梁はすべて125H鋼であり、構造躯体は現しとしない大壁仕様とした、素材も構造用合板に統一することで素材感をなくし、個々の建築要素が主張しない背景となることを目指した。 竣工後に何度か訪れているが必ず誰かが来ていて賑やかである。 1Fの作業場では旦那さんが畳をつくっている途中で材料屋さんが来て畳について何やら話をしている。 2Fに登るとお店では近所の方が商品を見ながら奥さんと雑談をし その上の全面畳敷の雑貨製造スペースでは畳でゴロゴロ休んでいる人の横でミシンにて雑貨が次々と作られている。 建築はその人の価値観や人柄が自然と滲み出るものであると思う。 住宅は勿論、店舗や作業場も同じで、ただ使いやすく効率的に物を生産できればいいというわけではない。 その場で物を生み出し、世に出ていく場としてどんな場が必要なのかを考えていくことが大事であると考えている。 そういう意味では風通しが良く、オープンで様々な人が引き寄せられる施主夫婦らしい建物になったと思う、 これからもこの建築の成長を共に見守っていきたい。